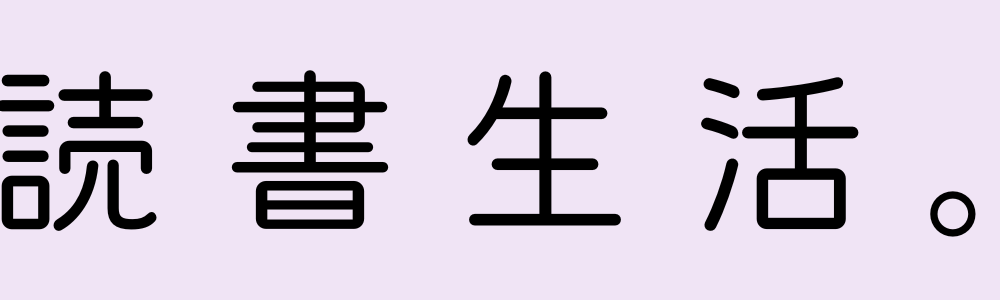私の書評記事の書き方は、間違いだらけでした。
読書ブログを開設して、一年以上が経ちます。
本の書評記事をせっせと書いてきましたが、悲しいことに…ほとんど収益が出ていません。涙
最近、やっと気づきました。
 チカチカ
チカチカ私の書評記事、書き方を間違ってた!
ということに。
(この一年は一体…)
今までの記事の何が間違っていたのか。
そして、これからはどんな記事を書くべきなのか。
全て、お話します。
何がダメ?間違いだらけの書評記事
私がこれまでに書いてきた書評記事の見出しは、こうです。
・作者や出版社について
・こんな人におすすめ!
・読んだきっかけ
・本の内容
・心に残ったポイント
・この本を読んで変わった!
・感想
…くどい!!
な、長すぎない?
一冊の本に対して、見出しが多すぎて。
読むのしんどくない?これ…。
自分的には、



情報量をいっぱい出して、本を掘り下げて、
お得感のある記事にしよう♪
というつもりでした。
今思えば、情報が多ければいいってものではなかったんですよね。
そもそも、この多すぎる見出し。
いっぱい削れるところ…あるよね?
①「読んだきっかけ」
→読者には関係ないのでは?
②「作者や出版社について」「本の内容」
→どちらも、Amazonや楽天、出版社などのサイトを見ればわかることです。
③「こんな人におすすめ!」
→おすすめされなくても読みたい人は読むし、なくても良さそう。
そもそも、見出しが普通で、興味をそそられない
……自分で突っ込んでおきながら、ダメ出しだらけでつらくなってきました。
いえいえ、現実と向き合わなくてはいけませんね。(キリッ)
この見出しの多すぎる書評記事。
本の詳細について知りたい人には、情報量が多くて良いかもしれません。
いっぽう、大半の人は、この書評記事を読んでも
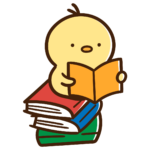
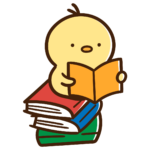
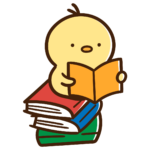
ふーん、そうなんだ…
で終わってしまうのでは?
長すぎて、最後まで読んでもらえない可能性も。(ガーン…)
どの記事も心をこめて一生懸命書いたものなので、全ての記事に思い入れがあります。
が、読者にはそんなことは関係ないんですよね。
一冊の本が教えてくれた!書評記事の本質
自分の書評記事の間違いに気づいたのは、この文章のおかげです。
決まったことをやる単純作業の部分は自動化されてしまうので、必要となるのはその仕組みや利益を生み出す方法を考えられる創造的な人だけです。
世界のニュースを日本人は何も知らない
谷本 真由美
こちらの書籍から引用しました。
「決まったことをやる単純作業の部分は自動化されてしまう」…
この一文を読んだときに、手が止まりました。
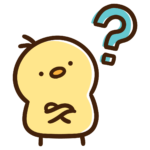
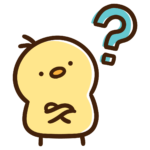
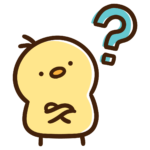
あれ?
この単純作業って、自分の書いている書評記事のことじゃない?
今まで書いてきた書評記事は、見出しを固定化することで
「見出しに合わせて記事を書く」
という単純作業になっていたかもしれません。
本の内容を紹介したり、
印象に残った箇所を引用したり。
それだけだと、どうしても「単純作業のような記事」になってしまうことがあります。
そこから一歩抜け出して、
「自分にしか書けない、唯一無二の記事」を書く。
そうすることで、創造的な人になることができます。



創造的な人になって、自分だけのオリジナリティを出した記事を書きましょう!
「自分にしか書けない記事」を書く


何を書けばいいの?
自分にしか書けない記事といっても、何を書けばいいんだろう?
ありふれた書評記事から、抜け出すために。
自分だけの強みを文章にするんです。
強みって言っても、特別に何かに詳しいわけじゃないし、専門家でもないし…。
大丈夫です。私も何の専門家でもありません。
他の人にはない、自分だけの体験や考えが強みになります。
何だっていいんです。
たとえば、
ネタは無限大にあります。
私のこの記事も、特別な知識がなくても書ける内容です。
ネタが決まったら、これをメインにして、記事を書きます。
まず自分の意見を主張してから、そのあとに
「この本が考えるきっかけになりました」
「この本を参考にしました」
と、さりげなく本を紹介します。
こうすると自分の意見がメインになるから、一見、書評記事っぽく見えないでしょ?
「書評に見えない書評記事」を書くことで、オリジナリティのある記事が完成します。
…そう、実は。
この記事も、「書評に見えない書評記事」なんですよ。
気づきましたか?😉
「書評に見えない書評記事」を書くことが、私の今の目標なんです💡
書評記事の書き方、どの順番で書く?
①書評を書きたい本を読む。
②本の中で、心に刺さった文章をしっかり読み込む。
③その文章から自分の考えや気づきを発展させる。
肉付けさせながら、感じたことや体験談を混ぜて記事を書いていく。
③が難しいです。
私自身、
「書評に見えない書評記事」を書ければ、オリジナリティのある記事になる!
と気づいた時も、



…えっ、そんなの難しくてできないよ!
と、ふてくされてしまいました。笑
ネタは無限大といっても。
日頃から独自性のあることばかり考えているわけじゃないし。
…と思っていたら、これが意外。
書きたいネタが、思い浮かぶようになりました。
自分の好きなことの話、
育児を通して感じたこと、
子どもの教育について、
自分の子どもの頃の話、など。
少しずつ、「これ書きたい」「あれ書きたい」が増えてきたんです。
何でもいいんですよね。
頭の中で物事を考える癖がある人や、
文章を書くのが好きな人なら、
ネタに困らないと思います。
それでもやっぱり難しい
ネタがあったとしても。
頭の中でぼんやり考えていることを言語化するのは、やっぱり難しいです。
私も、この記事を書くのに何日かかったかわかりません。笑
こまめに記事を更新できる人って、本当にすごいと思います。
最終的には、「継続は力なり」!
これです。
✓たくさん本を読んで、いろんな人の言葉に触れる
✓心に残った言葉や文章をメモする
✓自分で文章を書いてみる
✓今まで使ったことのない言葉を使ってみる(語彙を増やす)
✓文章に肉付けしていく
✓何度も推敲する
このくり返しです。
文章を書けば書くほど速く書けるようになるし、語彙も増えていきます。
いっぱい書いて、文章力を鍛えましょ💪
実例で比較!書評記事のビフォーアフター


さてさて。
一冊の本の書評記事を、異なるアプローチで書いてみたので、比較しますね。
①ビフォー:今までのスタイルの書評記事
本が主役の、見出し多めの書評記事です。
②アフター:新しいスタイルの書評記事
自分の考えが主役の、「書評に見えない書評記事」です。
まずは、
①今までのスタイルの書評記事
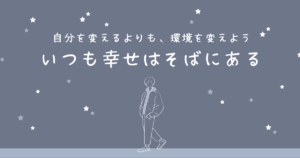
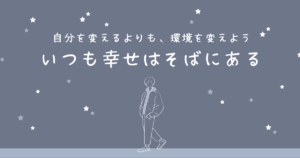
この記事の書き出しは、こうです。
自分の生き方はこれでいいのだろうか?
進むべき道はこっちで合ってるのだろうか?
そんな迷いがある時に、人生の指南書となる書籍をご紹介します。
たぐちひさとさんの『いつも幸せはそばにある』
です。
この書き出しの後に、
「作者や出版社は?」「こんな人におすすめ!」の見出しが続きます。
続きを読まなくても、このあとは、
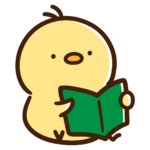
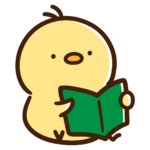
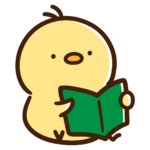
本のおすすめポイントや、感想を述べているんだろうな
ということが想像できます。
②新しいスタイルの書評記事
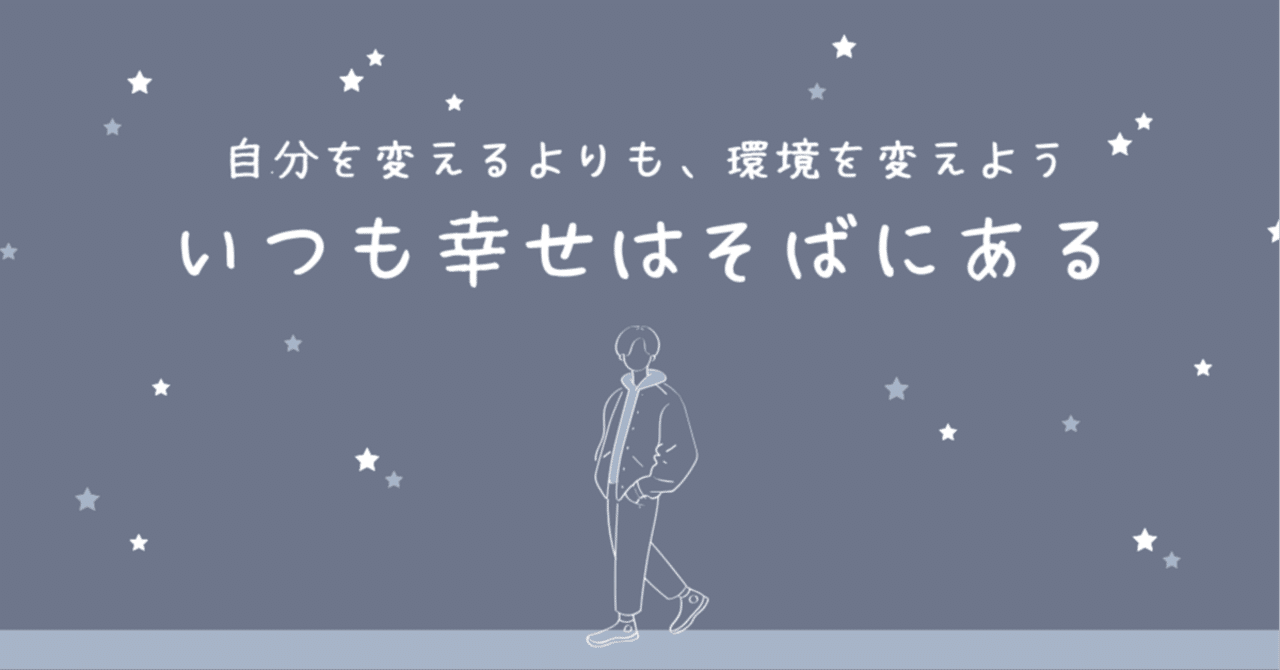
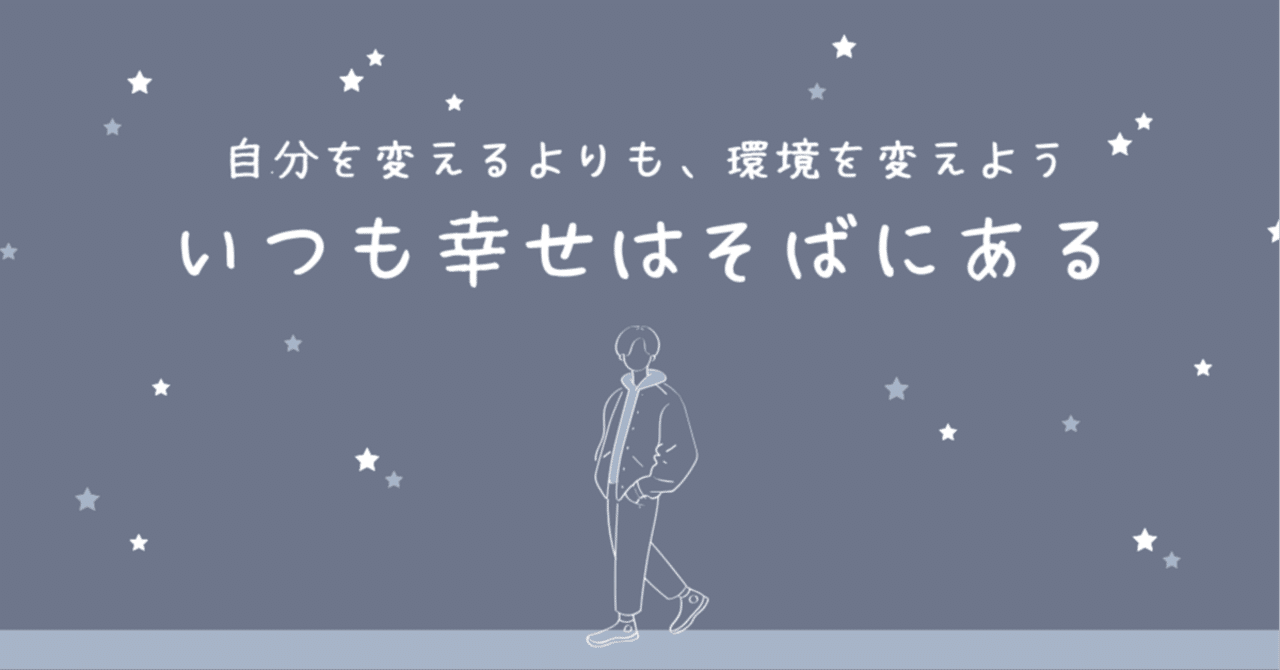
この記事の書き出しです。
「他人を変えることはできない。
だから、自分を変えることから始めよう」
自己啓発の本でよく見かける、この言葉。
うんうん、その通りだよね、とうなずきながら読んでいました。
…だけど、自分を変えるなんて、そんな簡単にできない!
人の性格や考え方って、たやすく変えられるものじゃありません。
今までの人生の積み重ねがあって、その人が存在しているのだから。
そんなことを考えていた時に出会ったのが、この言葉でした。
自分を変えようとするよりも
環境や人づきあいを
変えたほうがうまくいく
いつも幸せはそばにある たぐち ひさと
この書き出しには、
「自分を変えるなんて、そんな簡単にできない!」
という、悩みがあります。
そして、この悩みを解決する手段として、本を紹介しています。
読者は、この書き出しの続きを
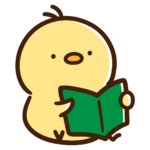
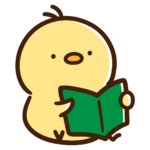
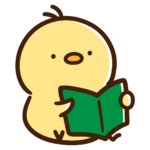
「自分を変えられない」という悩みを解決してくれるんじゃない?
どう解決してくれるのかな?
と期待しながら読むことになります。
どうでしょうか?
どちらの書評記事のほうが、続きを読みたくなりましたか?
同じ本のレビューでも、
ということがわかりました💡
それぞれのメリット、デメリット
上記で比較した、
①の今までのスタイルの書評記事は、本が主役です。
②の新しいスタイルの書評記事は、自分の考えが主役です。
どちらもメリットとデメリットがあるので、まとめてみました。
①本が主役の書評記事
✓その本に興味のある人に記事を読んでもらえる
✓「作品名」「著者名」で検索した人に見つけてもらいやすい
✓注目度の高い本だと、アクセスアップが狙いやすい
✓その本に関心が薄い人には、記事を読んでもらいにくい
✓そもそも、書評を読まないという人もいる
②自分の主張が主役の書評記事
(「書評に見えない書評」)
✓記事のタイトルで引きつけることができれば、本に関心の薄い人にも読んでもらえる
✓記事のタイトルに引きつけるものがなければ、読んでもらいにくい
✓キーワードの選び方によっては、検索結果で表示されにくい
記事のタイトル勝負!なところがあります。
②の「書評に見えない書評記事」は、その本に関心の薄い人にも記事を読んでもらえる。
これは大きなメリットです。
この②の書評記事の書き方、実践するのはなかなか難しいです。
だけど、難しい分、読みごたえのある記事になりますよ!
さらに、面白い記事を目指すために
何回も読みたくなる記事を書こう
自分の書いた書評記事を、読み返すことはありますか?
一度投稿した記事って、そのあとは放置したままになったり…していませんか?
私は、過去の記事を書き直したり修正したりする時は読みます。
普段はあまり読みません。そんなに読みたいと思わない。今までは、そうでした。
ふと、思いました。
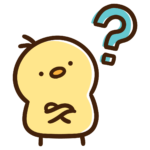
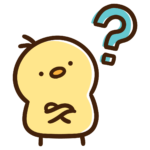
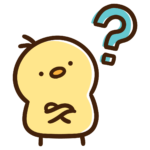
自分が読んでいない記事を、誰が読みたいと思ってくれるんだろう?
一回読んだら終わり、じゃなくて。
何回も読みたくなるぐらい、面白い記事を書かなきゃいけないんじゃない…?
自分のnoteのアクセス数を見てみると、
「上手に書けた!」
「自信ある!」
記事は、やっぱり読者の反応がいいんですよね。
読者には、著者の熱量や工夫が伝わります。
というわけで。
自分で、



この記事、面白い!
何回も読み返したい!
と思える、自信をもって紹介できる記事を書きましょう♪
客観的な視点で読む
自分の書いた記事が、面白いのか面白くないのか、よくわからない!
そんな時は、
記事を寝かす。
これに尽きます。
私のnoteで一番多くスキをいただいた、自己紹介の記事。
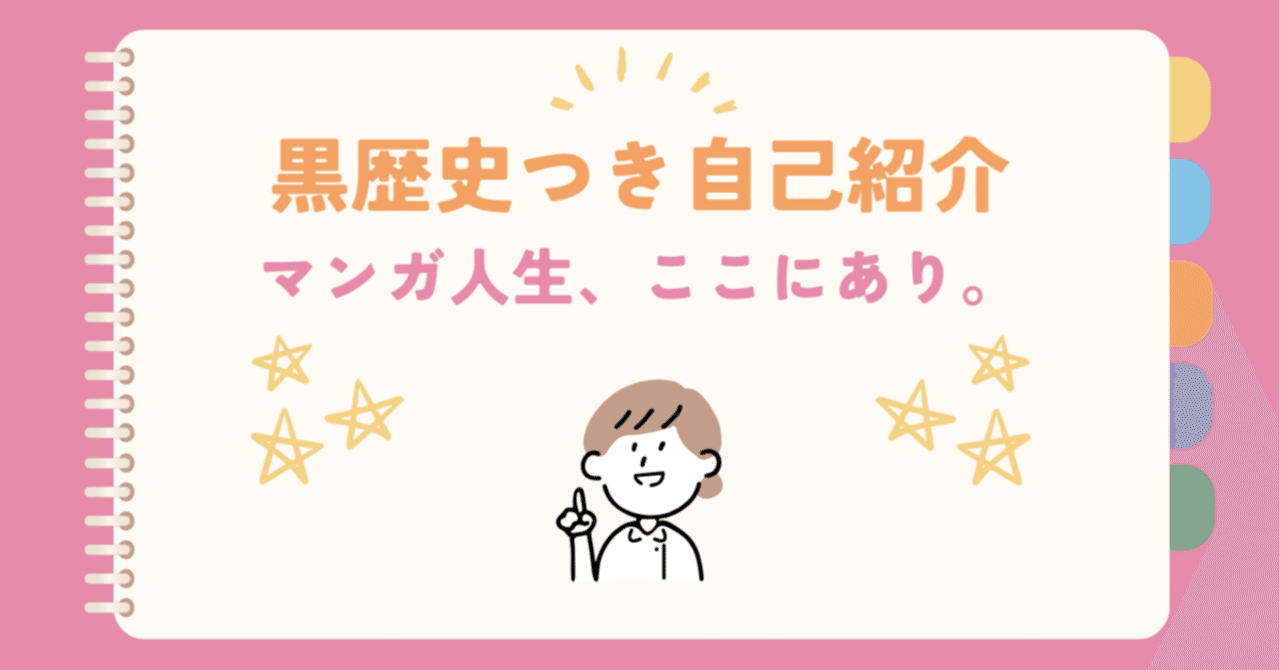
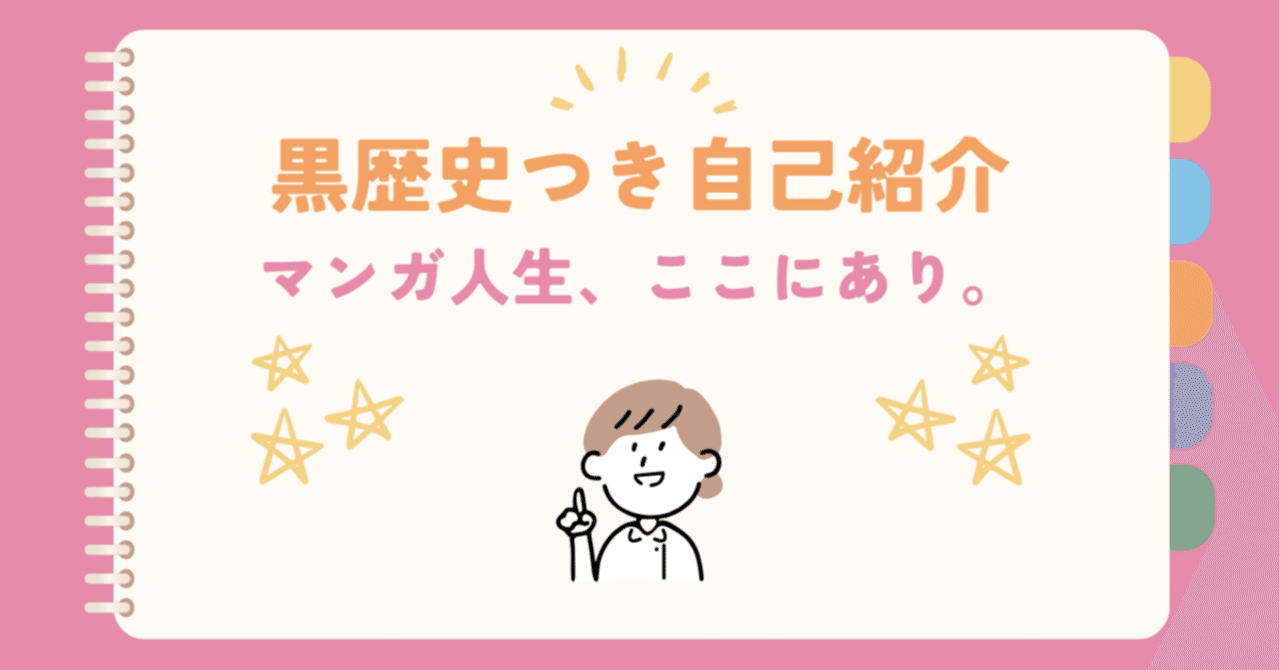
この記事、何日もかけて、少しずつ下書きをしていました。
でも、この自己紹介…面白いのかな?
自分の恥をさらしているだけじゃない?
面白いのか面白くないのか、よくわからなくなって、記事を公開しないまましばらく寝かしていました。
それが、自己紹介記事の公開が遅くなった理由です。
日にちを置いて読んでみたら、
「これ、面白いかも!」
って初めて思えたんです。
それで、きちんと書いて記事を完成させました。
日にちを置くと、客観的な視点で読めるようになりますよ。
今後の書評記事の書き方
これからは、読書ブログとnoteで書評記事の書き方を変えていこうと思います。
読書ブログでは、
・見出しを減らした書評記事
・本が主役の記事
noteでは、
・書評に見えない書評記事
・自分の考えが主役の記事
読書ブログのほうは、自分の備忘録的な意味合いが強いです。
そして、その本に関心のある方に読んでいただけたらうれしいなと思います。
noteでは、読んでもらえる文章を意識して書いて、多くの方に読んでいただくことが目標です。
書いていて大変なのは「書評に見えない書評記事」のほうだけど、
書いていて楽しいのも「書評に見えない書評記事」だったりします💡
この記事もどんどん書きたいことが増えて、ついに5,000文字を超えました😳🖋️
自分の考えが主役なので、どんどん自分の主張を盛り込むことができるのが楽しいです。
本が主役の書評だと、自分の主張は控えめにしないとな…と抑えめにしてしまうので。
私もまだまだ試行錯誤中です。
記事を書く時は、
上手に書けるかな?
自分の気持ちを上手く伝えられるかな?
と、毎回ドキドキしています。
書評記事を書かれているみなさん。
一緒に頑張っていきましょうね!



最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊