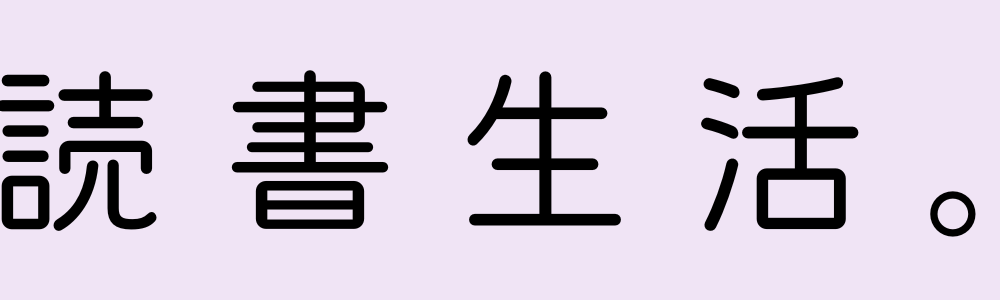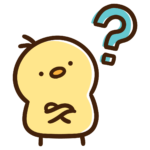 チカチカ
チカチカ本を読んだのに、時間が経つと何が書いてあったのか忘れてしまう…
そんなことはありませんか?
この悩みを解決してくれる、読書術の本を2冊ご紹介します。
です。
おすすめ①
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書
作者の西岡壱誠さんはもともと偏差値35、そこから2年の浪人生活をした後に東京大学に合格されています。
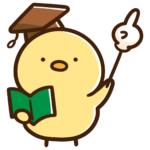
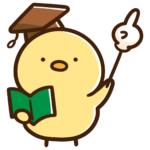
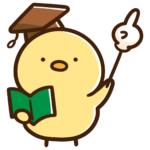
そんな経験のある西岡さんだからこそ、本書は説得力のある内容になっています!
おすすめ②
「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命
金川さんは大学在学中に公認会計士試験に合格、世界一の規模の監査法人トーマツ勤務を経て独立。
『YouTube図書館』というチャンネルで本の紹介をされていて、チャンネル登録者数はなんと17万人を超えています。(2025年2月現在)
現在も頻繁に動画をアップされていて、動画は20分超えのものばかりです。
これは、速読かつ本の内容をしっかりと理解されているからできることなのではないでしょうか。



かなり効率的な読書術を教えてもらえそうです。
これは期待大!
こんな人におすすめ!
本を読むのに時間がかかる
読んだ本の内容を忘れてしまう
本の内容がいまいち理解できない
自分の読書法に迷いがある
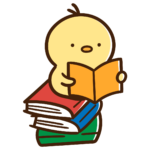
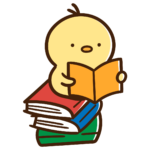
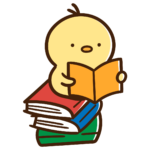
管理人は、本を読んだ後によく「あれ?結局何が書いてあったんだっけ?」となっていました。
それがきっかけで読書術に興味をもつようになりました!
・自分の読書法が見つかる!
・読んだ本の内容を覚えていられる
・本が速く読めるようになる
読んだきっかけ
『東大読書』…本屋で見かけてタイトル買いしました。「東大読書」はタイトルのインパクト大です。
『読書革命』…「東大読書」以外の読書術の本にも興味が湧いてネットで検索したところ、高評価レビューが多かったので気になって購入しました。
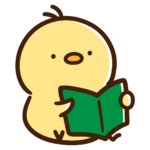
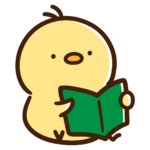
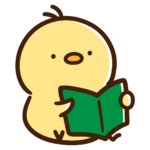
自分の読書法を変えたくて買いました!
本の内容は?2冊の本を読んでわかることは?
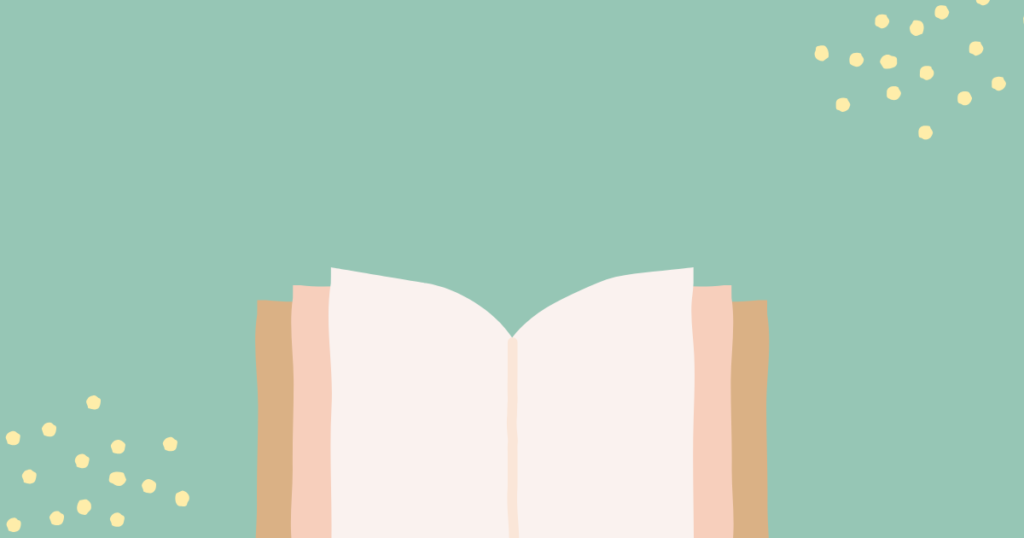
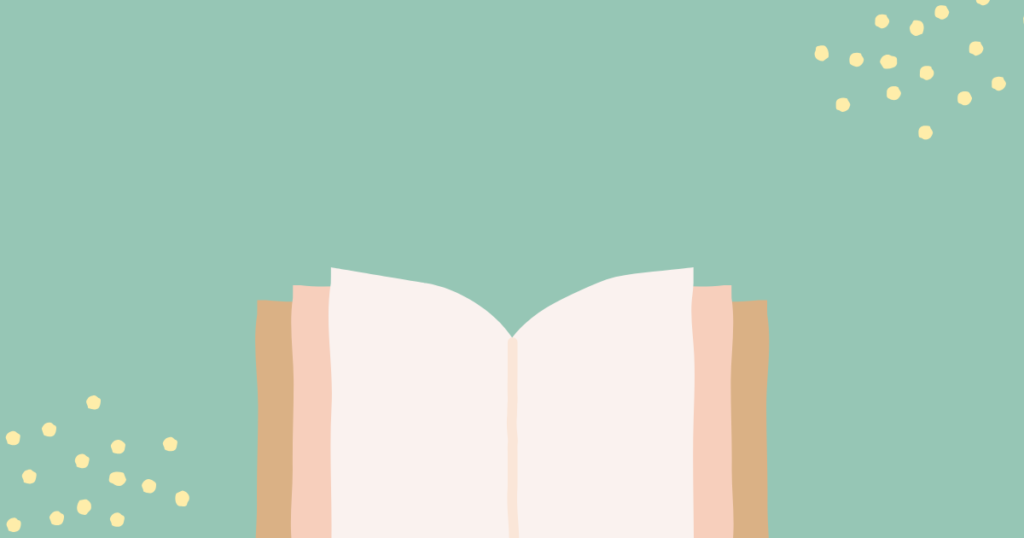
どんなことが書いてある?
『東大読書』『読書革命』では、それぞれ下記の段階に分けて読書することを提案しています。
| 『東大読書』 | 『読書革命』 |
|---|---|
| ①仮説作り ②取材読み ③整理読み ④検証読み ⑤議論読み | ①予測読み ②断捨離読み ③記者読み ④要約読み |
どちらの本も「受動的な読書」ではなく、「能動的な読書」を推奨されています。
さらに、それぞれの本で記載されている読書の特徴をまとめました。
| 『東大読書』 | 『読書革命』 |
|---|---|
| ・本と議論する ・読む前の準備で読解力が上がる ・「記者」になったつもりで読む ・本の要約をすることで情報を取捨選択できるようになる ・アウトプットで読解力が向上する | ・まず「はじめに」「おわりに」、目次に目を通す ・本をめくって気になったところを熟読する ・1冊の20%を読むことで本全体の80%を理解する ・読書によって思考の軸が鍛えられる ・アウトプットこそが最高のインプット |
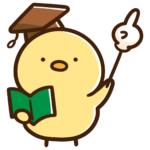
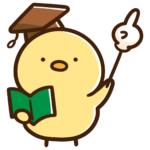
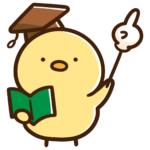
共通しているのはアウトプットを重視している点ですね!
この2冊を読んで変わった!
何が変わったの?


読書の質が高くなった!
今まではぼんやりと本を読んでいた
↓↓↓
能動的な読書に変えただけで、集中力&理解力が高くなった!
アウトプットを意識しながら本を読むようになりました。
私の場合は
アウトプット=ブログの記事を書くこと
になります。
ブログを書くために「どこを記事にしようかな?」と集中して読みますし、自分の理解が合ってるかな?と確認するために何度も何度も読み返します。
アウトプットを意識することで、今までみたいにぼんやりとは読めなくなりました笑。
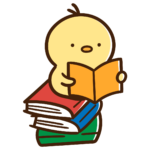
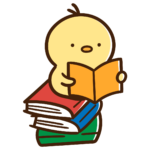
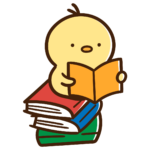
他にも、作者は何を一番伝えたいのか、どこが大事なところなのか等を考えながら読むようになりました。
集中して真剣に読めば読むほど、頭に入りますし残ります。
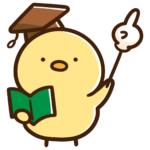
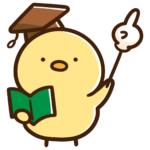
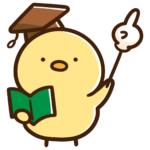
ブログをやっていない方にも、何らかの形でアウトプットすることをおすすめします!
自分の読書スタイルができてきた
今までは前から順番に本を読んでいただけだった
↓↓↓
一番最初に「はじめに」と「おわりに」を読む癖がついた
本に付箋を貼ったり蛍光マーカーでチェックしながら読むようになった!
最初に「はじめに」と「おわりに」を読む癖がついた
『読書革命』から引用します。
まず「はじめに」を先に読みます。なぜこの部分を読むかというと、本の冒頭部分に問題提起や解決策が書かれているからです。
「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命
金川 顕教
そして次に「おわりに」を見ます。大体「おわりに」は「自分が言いたかったのはこういうことなんです」と書かれています。
「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命
金川 顕教
「はじめに」を読むと、この本は何について書かれているのか概ねわかります。
「おわりに」はまとめ、結論ですね。
つまり…



最初に「はじめに」と「おわりに」を読むことで、本の全体像をつかむことができます♪
本に付箋を貼ったり蛍光マーカーでチェックするようになった
・付箋で残しておくと、頭に入りやすく、記憶に定着する
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書
西岡 壱誠
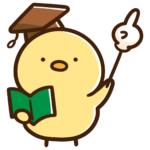
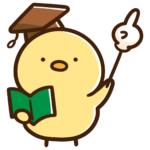
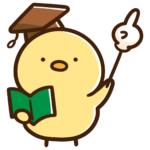
本を読んでいると「この文章が特に印象に残った!」「ここ共感する!」など、お気に入りのページってあるよね。
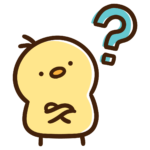
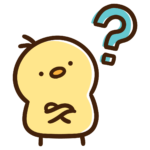
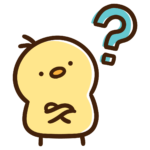
あるある!でも、本を読み終えて時間が経つと忘れちゃうんだよね。
なんでだろう?
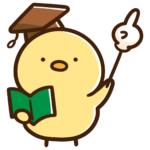
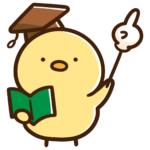
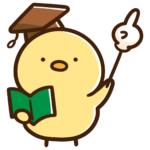
時間が経つと忘れるのはみんな同じだよ!
あとですぐにわかるように、お気に入りのページに付箋を貼ったり蛍光マーカーでチェックしよう。



それなら本を手に取った時にすぐにわかるもんね!
その結果、私の読んだ本にはどれも付箋がびっしり貼られています。
付箋が多すぎてもお気に入りのページを探すのにも一苦労するので、そんな時のために。
付箋の端に、蛍光マーカーでチェックした文章の一部や単語をメモすることをおすすめします!
単語をメモしておくと、すぐに思い出せるので便利ですよ♪
感想
読書術の本は、読者が本を読む時に手助けをしてくれる!
アウトプットするまでが読書なんだ!
と言いますのも…
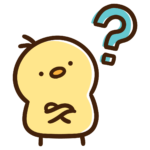
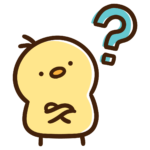
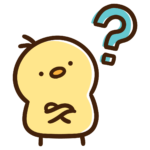
自分の読書法はこれでいいのかな?
と迷っている人、きっと多いと思うんです。
もちろん私もそうでした。
このレビュー記事で紹介した読書術の本を読み込むうちに、
「この読書法だと本の内容を覚えていられる」
「自分にはこの読書法が実践しやすそう」
と、自分の読書スタイルを見つけることができるようになってきました。
読書術の本を読まなかったら、今も自分の読書法に迷いがあったのでは?と思います。
そして、アウトプットの重要性についてはどちらの本にも書かれていますので



本の内容を忘れないためにはアウトプットこそが大事!
アウトプットするまでが読書だ!
と考えるようになりました。
最後に、私が「これは名言だ!」と感じた文章を引用でご紹介します。
「インプット」を自分の知識にするのが「アウトプット」であり、また「アウトプットしよう」と考えるからこそ「インプット」の質も高まる。
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書
西岡 壱誠
読書は知識を得るためではなく思考を磨くためにする
「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命
金川 顕教